ふわりと漂う、薔薇の香り。
ゆっくりと目を開けると、窓からは夕暮れの紫に染まった空と、バルコニーの手摺りに絡まる荊の蔓が見えた。
身体を起こそうとして視線を正面にやり、中空にうっすら映り込んだ自分の姿が視界に入る。
「何だこれ……ガラスの、板……?」
目の前の硝子板にも驚いたが、先ほど映り込んだ自分の姿には微かに違和感があった。しかし、違和感を確かめる前に、涙声の少女の声が割って入る。
「ルージュ! ……良かった! ほんとうに……」
見慣れた緑髪と、ルージュの瞳とは少し趣の違う、少し橙を帯びた朝焼けのような赤茶の瞳。少女の目からは大粒の涙が次から次へと零れ落ちている。声には鼻を啜る音も混ざっていた。どういう仕組かはわからないが、先ほどまであったガラスの天板が消えている。身を起こして、自分がいた場所が針の城だということに気が付いた。
「このまま、起きなかったらどうしようって……」
「ごめんアセルス、ブルーは?!」
アセルスは一瞬だけ目を大きく見開いた後、はあ……と溜息を洩らした。
「起きてすぐいうことが、それ?」
まあいいけど、とアセルスは、ルージュの隣に並べられた透明な棺を示す。
「ブルーの体はそこ」
蔓薔薇に覆われた硝子の棺の中に横たえられたブルーは、着換えさせられたのだろう。対決時に纏っていた蒼の法衣ではなく、ルージュが着ているのと同じような白の夜着姿だった。流石に、血やら何やらで汚れたままにはしておけなかったらしい。
「……眠ってるみたいだ」
「まあ、眠ってるに近い状態だからね」
アセルス曰く、寵姫のための硝子の棺は、中に納める者を仮死状態に保ち、外界の干渉を遮断する働きがあるらしい。
対決の後、瀕死の重傷ではあるものの、かろうじて息のある状態のうちに、ブルーとルージュは針の城に運び込まれたのだそうだ。
「城の中には、許可なく入ることは出来ないからね」
(たしかに、僕たちを隠しておくには絶好の場所ではあるよね……城主はアセルスだし)
見て、と差し出された鏡を見て、ルージュは言葉を失った。
紅色だった自分の瞳が、ブルーのものとも自分のものとも違う、夜空のような濃紺に染め換えられている。
「今の貴方――正確には『貴方たち』だね。私は難しいことはよくわからないから」
慣れた手つきでアセルスが呼び鈴を揺らすと、近くの扉から侍女が現れた。
「ヌサカーンを呼べ。ルージュが目を覚ました」
ルージュがブルーと対峙したあの場所は、どのリージョンでもなく、マジックキングダムでもない、閉鎖された特殊空間だったらしい。
何度か倒れ込んだ記憶はあったが、どうやらその度に傷が癒えていたのは、場に施された特殊な結界の効果らしい。傷を癒すには、対象者の命を削る――文字通り、殺し合うための舞台を整えられていたということだ。だが、場に施されていたのはあくまで、決闘のためにどちらかの命が尽きるまで戦い続けることを強制する効果しかなかったらしい。
「大変だったんだよ? 二人とも死にかけてるのに治療を施そうにも傷薬も回復術も弾かれるし、センセイの白衣も効かなかったから」
「待って、ブルーも、瀕死って――」
あの場でルージュは確かに、何度も昏倒した記憶はある。けれど、ブルーが倒れたのは――
「まさか――ブルーは」
「我々は止めたんだがね。時術の資質を得るために、砂の器が必要になったとき、ブルーは『どうせ一つも二つも大して変わらん』と」
あの時――ブルーが携行していた紅の魔剣。あれは、ブルーの命を代償に得たものだったのだ。
(どうしてブルーは、そんな――自分の命を極限まで削るようなことを)
「瞳の色の変化については、妖魔の君の寵姫になったからでは無いから、安心していい。禁忌の融合の結果、髪の色や瞳の色に変化が出るらしい――とはブルーから聞いているが、君たちの場合は瞳が顕著だったようだ」
「ブルーから?」
ルージュが目覚めるより先に、ブルーが先に目覚め、自分たちに起きた事象をかい摘んで説明していたらしい。「今はブルーの意識――正確には魂の部分だが――ブルーの自我はルージュと半ば融合しかけていて、ルージュに意識が無いときはブルーの意識が表層に出ることが出来る。つまり、ルージュが眠っているからブルーが表層に出ていて、逆にルージュが目覚めれば、肉体の主導権はルージュに渡る」のだと。
あの対決の場では、どちらもいつ死んでもおかしくない重傷を共に負っていた。
だから本来はどちらかの肉体が塵と化してから発動する筈の魂の融合が先に為されてしまった――ということだった。肉体の融合を防ぐためと、そのまま二人とも死亡するのを避けるために、緊急避難的に融合しかけた魂を体に放り込んだ結果が今の状況とのことだ。
「それでどうして、ブルーでなく、僕に?」
「単純な話、君の方がまだ傷が浅かったからだ。患者の生存率を上げるためには至極まともな判断だろう?」
思ったより普通の理由で、ルージュの肩から力が抜ける。
「あの特殊結界の中から出たあとも、二人の意識が無いまま治療を施そうとしても、どちらかがどちらかを取り込もうとしていたし。止めるためには、私とヌサカーンの妖力でそれぞれ仮の棺を作って、お互いの干渉を止めるしかなかったんだ」
吸血妖魔でないヌサカーンにそんな能力があるのかと驚きはしたが、妖術のひとつである「硝子の盾」の応用で、作り出すこと自体は大して難しくはないそうだ。双子に施された術式は魔術で構成されているものであるため、魔術の干渉を避けるには、相反する性質を持った妖術の力を使うのが一番確実だということだった。
ルージュの棺をアセルスが、ブルーの棺をヌサカーンがそれぞれ作成したのは、念には念を入れて、アセルスの配下に無い妖魔の妖力を使うため、だったようだ。
寵姫のための棺が特別なのは、棺に纏う吸血薔薇の存在だ。通常硝子の棺は、針の城の主たる魅惑の君からの吸血を受け、寵姫となったものが棺の中で眠りにつくときに使われるものだ。吸血薔薇が中に収められる寵姫から妖魔の血を吸うことで、本来は睡眠も不要とする妖魔も意識を失い、人間でいうところの深い眠りについているのと同じ状態になる。しかし、双子の延命措置のために施されたのは、薔薇を通じて針の城全体に漂う妖力から、中に居る者の生命維持に必要な生命力を補わせるための働きだった。
ルージュが目覚めて最初にアセルスが駆け付けたのも、棺の薔薇を通じて目覚めを感じ取ったから、らしい。
魔導王国がどうやってそんな術式を開発したかは分からないが、双子にのみ発動する禁忌の融合術は、効果を見るにモンスターの吸収融合に近い働きをしているのではないだろうか。
「つまり、君たち二人には、『対象者二名が同じ空間に存在する状態で、相反する資質を得ており、かつ、どちらかの命が尽きる直前に、どちらか一人に二人が修得した資質を取り込む』という、人為的な処置が施されていたということだ」
――知りたい。行かなければならない。すべての始まりの、魔導王国へ。
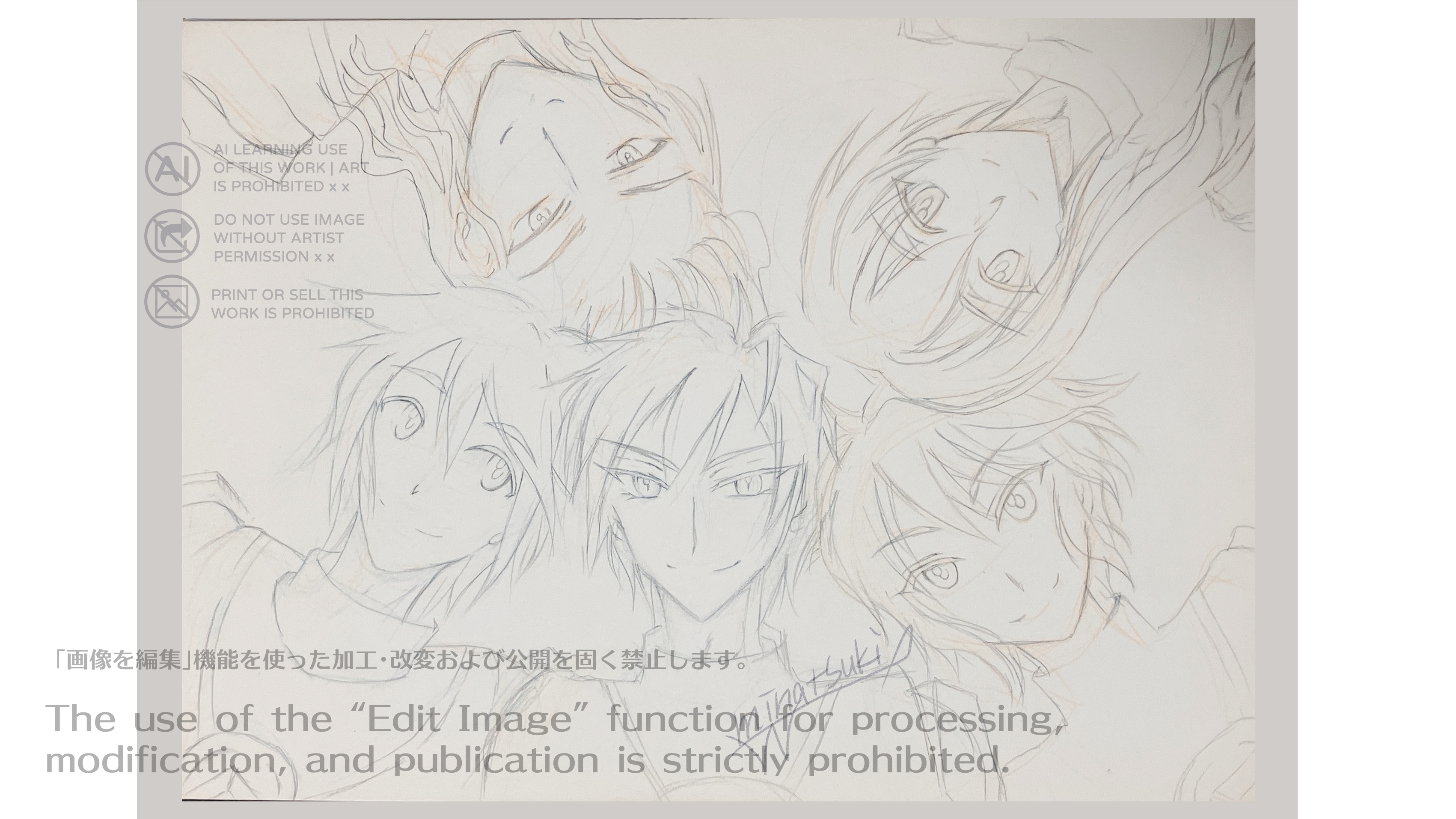

コメント