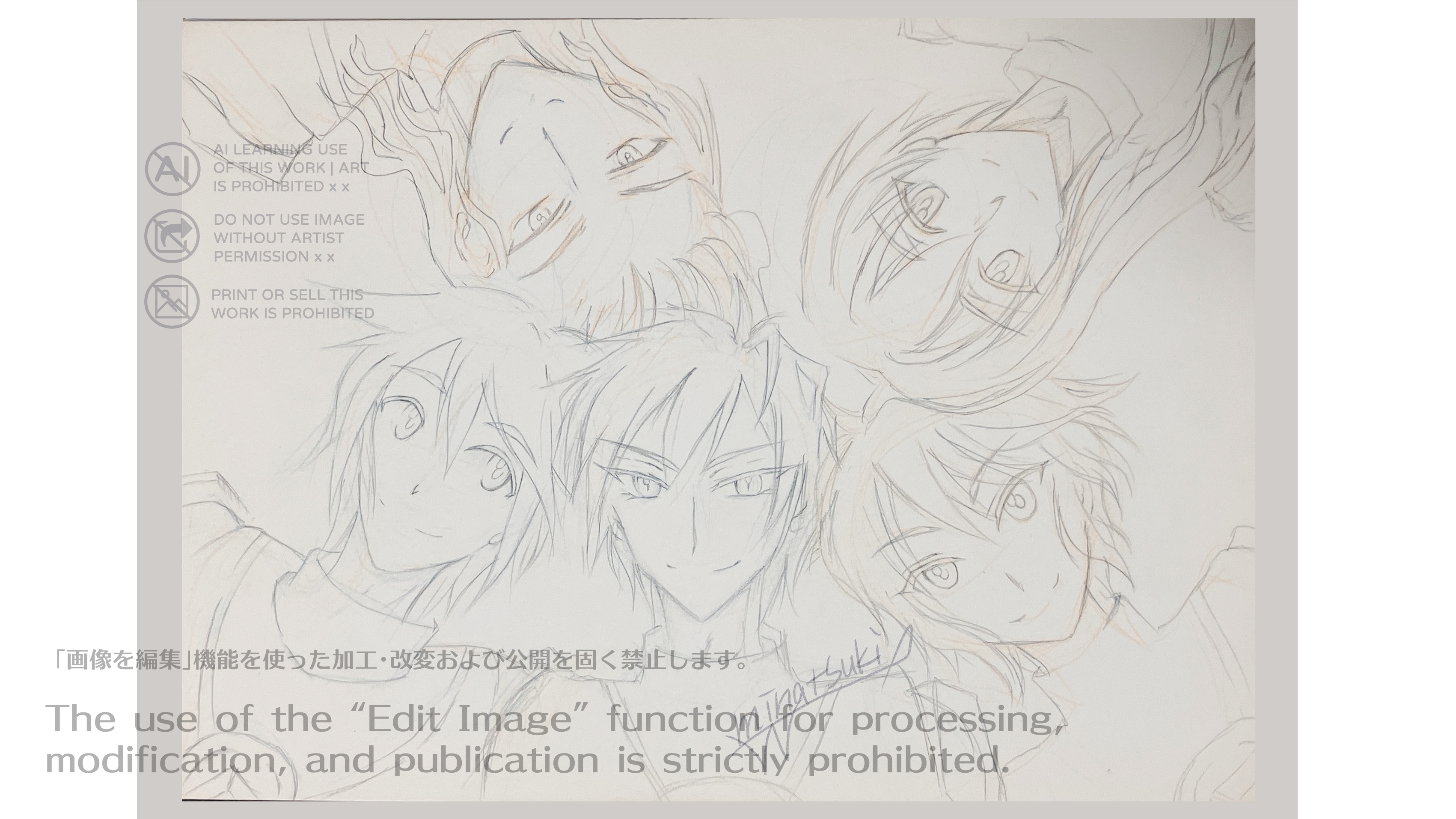孤城
リージョンシップの中で一息つくと、IRPO捜査官のヒューズはかねてより気になっていた疑問をぶつける。
「……そういや、前々から気になってたんだが、なんで盾のカードがIRPOにあるって判ったんだ? ありゃ確か、借金のカタに差し押さえたっつー、いわくつきのシロモンだぜ?」
もっともその借金のカタに差し押さえたっつー高利貸しが、資質会得の巡礼に嫌気がさしてお役所に持ち込んだんだけどよ、 とヒューズはボソリとつぶやく。
盾のカードを求めてやってくる巡礼にうんざりしていたのはお役所の方でも変わらずだった。
どう高く見積もってもハイティーンだろうというアセルスと、洗練された立ち居振舞いから、 相当上の方の階級の出身であることが伺える白薔薇。
そして、どうにも世間知らずな、人の良さそうな学生上がりの魔術師と、隙の無い中にもどこか人を和ませる不思議な雰囲気を持った青年。
およそギャンブルや裏事情に詳しそうには見えない一同の顔ぶれを見ると、 どうもその筋からの情報ではないらしい。
「――秘術の資質を得るためには、『盾』『杯』『金貨』『剣』、 それぞれの図案を白紙のカードに刻まなければならない。 マスターカードの在り処は常にドウヴァンの占い師の老女が把握しているため、 マスターカードの持ち主の元には資質を求めるものが次々とやってくる、というわけだ」
ヒューズの疑問に、ジェラスは簡潔に答えた。耳に低く響く、心地よい声だった。
ふーんと思わず納得しかけて、ここ数日の受付の慌ただしさを思い出したヒューズは冗談じゃないと抗議する。
「だったらんなモン、自分で管理しときゃいいじゃねェか! っかー、いけ好かねぇババァだな!」
「……それでは試練にならないだろう」
やれやれ……と呆れたように言うジェラスに、アセルスもびっくりしたように目を丸くする。
「試練?」
当のルージュはと言うと、何故か先程からまとわりついて離れない金の鳥をどう扱ったものかと困惑気味で、会話の内容など右から左だった。
ジェラスは一度目を伏せ、慎重に言葉を選びながら話を続けた。
――術を極めることを至上の研究目的とするマジックキングダムにおいては、学生は他のリージョンへ渡ることは許されない。
しかしそれでは、多種多様な術の研究をするのに不都合だ。
現に、特定の場所でのみ得られる資質がある以上、研究者を外に出さない訳にもいかない……
だからキングダムでは、幼い頃から術に関する英才教育を施した上で選抜を行い、特定の優れた術士のみに一定期間のみという制限を課して 資質修得の試練――最終試験として他リージョンへの外遊を許可する、というシステムが出来上がっている――
ジェラスの説明で納得したというようにアセルスは手を打った。
「だからルージュって、やたら難しいこと知ってる割に『何でそんなこと知らないの?』ってぐらい、簡単な常識知らなかったりするんだね」
金貨のカードを得るために寄ったカジノでの慌てぶりと、ショッピングモールでのルージュの様子を思い出しながら、アセルスはくすくすと笑う。
「じゃぁ、次は杯?」
アセルスの提案に、ヒューズが待ったをかける。
「いや。ヨークランドみたいなのどかな田舎町に、朱雀を連れて行くのは目立ちすぎるだろ。 クーロンあたりだったら、裏通りどころか表にスケルトンの用心棒がいるぐらいだからたいして目立ちゃしねぇけど」
流石にIRPOにいるだけあって、ヒューズは各リージョンごとの事情に詳しい。
「杯のカードはヨークランド、剣のカードはワカツ。――どちらにしてもクーロンでの乗換えが必要だな」
リージョンシップの航路案内を見ながら、ジェラスも同意する。
しかし、クーロンのシップ発着場で、ワカツ行きを告げたとたん、受付嬢の表情が曇った。
「……恐れ入りますがお客様、ワカツは現在、大変危険な状態になっておりまして、とても踏み込めないのです。 土地に慣れたものの案内なしではシップの発着は出来ません」
「だってさ。どうする、ルージュ? 先にヨークランドへ行っちゃおうか?」
受付嬢の言葉を受けて、アセルスは仲間の方をふりかえる。
そのとき、割って入る声があった。
「おう、おめえらワカツへ行きてぇのか? だったら俺が案内してやるよ!」
受付で立ち往生している一行に声をかけてきたのは、鉄下駄を履いた中年の男性だった。
「おいおい。おっさん、アンタ相当酔っ払ってるね? ワカツって言えば古くから知られた剣豪の里じゃねェか」
腰から酒瓶下げてても剣の一本も持ってねぇのに何言ってんだか、とヒューズは笑った。
(この人、強い……!)
アセルスは、自身も剣を使う身であるので相手の身のこなしからおおよその力量も推測できる。
酒瓶を下げた男の足運びは、はいているのが鉄下駄ではなく草履だと言われても信じてしまいそうなほど軽やかで。鉄下駄の重みを感じさせないだけでなく、重心の移動――上半身にも下半身にも、全く体幹のブレが無いのだ。
「おじさん、ワカツの人なんだね?」
「おうよ!大船に乗ったつもりでまかせろ! でもな嬢ちゃん、おじさんはやめてくれ。俺はゲン。ゲンさんでいいぜ。案内の礼はヨークランドの酒でいいから よ」
豪快に笑うゲンに、アセルスもつられて笑顔になった。
そして向かった先――ワカツ。
かつて剣豪の里として知られたこのリージョンはトリニティに滅ぼされ、いまでは死者の怨念渦巻く魔窟と化していた。
「剣の資質は天守閣、剣聖の間だ」
ゲンの案内で、一行は崩れかけた城内を進んで行った。
「正直、私やルージュには少々、きついな……」
「うん……ここの念の強さは並じゃないよね……。いくら普通の人でも、長時間いたら体調を崩すよ」
術士として、ふだんから感覚を研ぎ澄ませている2人にとって声無き声で訴える無念は、それだけで刃となって精神に届く。
壊れかけた城門をくぐり、階段を登って2つ目の踊り場に差し掛かったとき、先頭を歩いていたゲンはふと足を止めた。
「どうしたのゲンさん?」
「何だよ何も――って、うわっ!」
アセルスがゲンに続いて顔を出し、ヒューズが文句を言おうとした途端、唐突に出現した影。
「あ、貴方は……!」
それは、アセルスと白薔薇が良く見知った妖魔の青年だった。