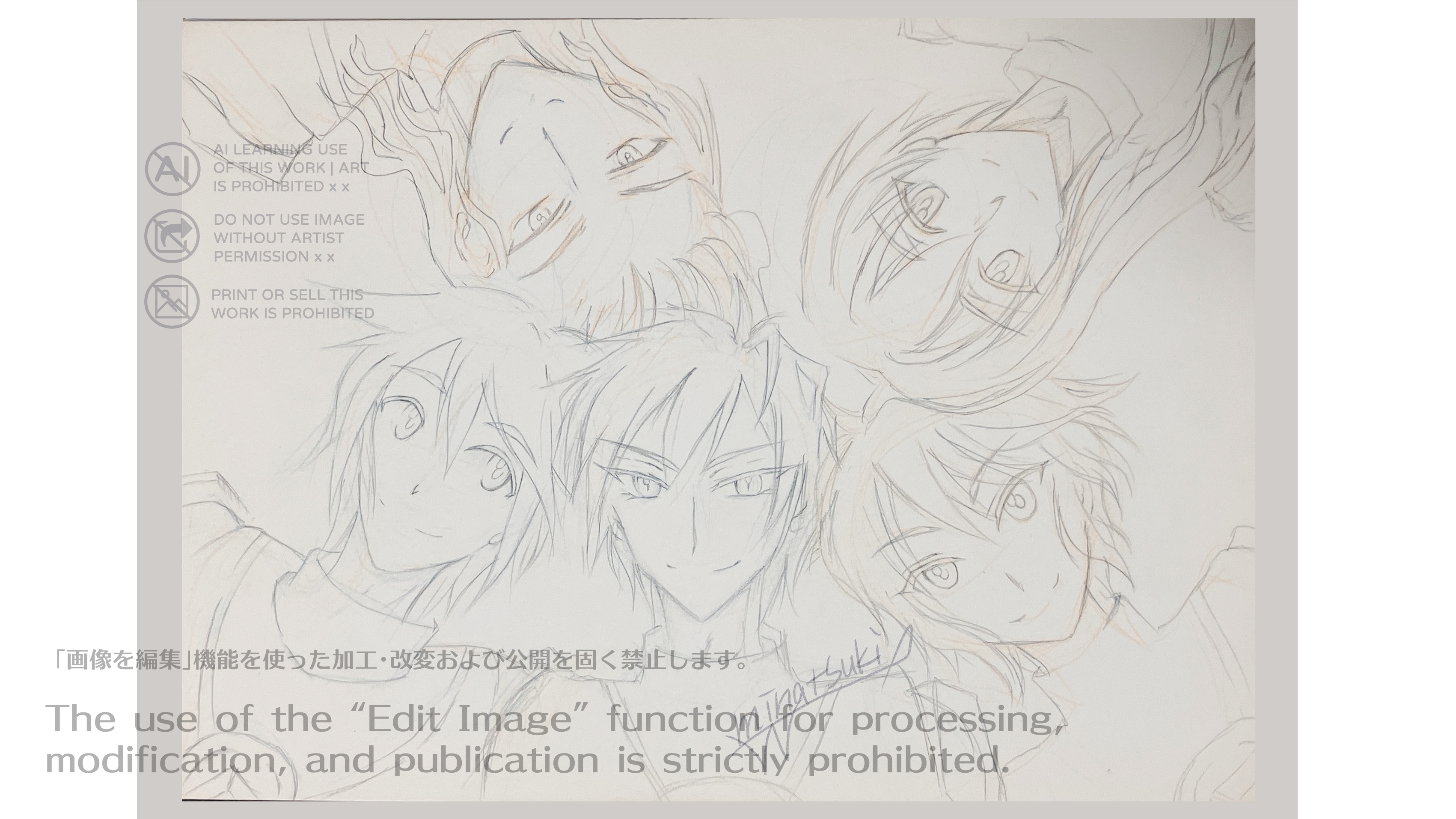別離
アセルスとルージュ――ふたりはドウヴァンの神社に来ていた。
赤い鳥居の影から、イルドゥンが姿をあらわす。
「もっとしゃきっとしろ! 見ていて少し、歯がゆいぞ!」
長い長い石段を登った先にある、赤い鳥居の、さらに先。
ふわり、ふわりと、幾枚もの色づいた葉が舞う境内。
日が少し傾きかけているのと、落葉の照り返しの影響だろうか。ルージュの銀髪が金髪のようにも見えた。そして、アセルスの口を衝いて出た何気ない質問。
「あのさルージュ。……キミってお兄さんか弟、いる?」
ほんの一瞬だけ、ルージュの顔が強張り――彼が何か言いかけたところで、聞き覚えのあるバリトンの声が割って入った。
「どうした? そんな顔して。らしくないな、お嬢さん」
穏やかな笑みを湛えた黒髪の青年――ジェラスが、境内に植えられた樹にもたれかかるように立っていた。
斜めに差し込む、柔らかな光のなか――夜の闇を思わせるような影。
黒の影が異質さではなく、この穏やかな空間に自然に溶け込んでいるのは、彼のもつ雰囲気のせいだろう。
「みんな……ありがとう」
目の端に浮いた涙を拭うと、アセルスは「疲れたから先に宿へ行く」と告げ、石段を降りていった。イルドゥンも無言でそれに続く。
一方、動こうとしないジェラスに、思案顔でルージュが話しかける。
「初めて会った場所に、似ていますね」
ああ、と黒髪の青年はルージュの方に顔を向けることなく微笑んだ。
その横顔がほんの少しだけ淋しそうに見えて――ルージュはきっとこの落葉のせいだ、と自分に言い聞かせた。
「……求める資質は、残りひとつ」
独り言のように、ジェラスは呟く。
「全ての資質を得たとして、何をする?――いや、どうしたい? ルージュ」
視線を目の前の樹に向けたまま、ジェラスはルージュに問う。
「僕は」
旅の間中、あえて目を逸らしつづけてきたことを突きつけられて、ためらいがちにルージュは言葉を紡ぐ。
―――古い知り合いにキングダムの卒業生がいてね。
―――友人を助けられなかった分、手助けがしたいと言ったら、迷惑か?
初めて会ったときの、ジェラスの微笑がルージュの脳裏に甦った。懐かしいものを見るような安堵と、わずかに哀しみの混じったような複雑な笑顔。
(ああ、この人は。『双子の宿命』を知っていたんだ……)
「僕には……ブルーと対決するための資質をすべて手にしたとしても、ブルーを殺すなんて、出来ない」
足元に視線を落としたルージュはようやく、搾り出すように問いかけに答えた。
しかし掠れた声でそうじゃない、と呟くと目を伏せ、かぶりを振った。
「いや、違うな……。そんなこと『したくない』んだ……」
「そうか」
歯切れの悪さに気付いてはいるが、ジェラスは先をうながすでもなくルージュが続きを言うのを待った。
問いかけ、というよりは――まるで独り言のように、ルージュはぽつりぽつりと呟きをもらす。自分の中で考えをまとめるかのように。
マジックキングダムが必要としているのは……ふたりの優秀な不完全な術士ではなく、完全な一人の術士。
通常、相反する術を同時に一人が身に付けることは出来ない。だが、マジックキングダムで生まれた双子に限り、資質を得ることが可能となっていた。
お互いに相反する資質を集め、相手の持つ資質を吸収する。
双子の片割れをその手で殺し、力を奪うことで。そうして得られる、究極の術と『完全な術士』。
「……キングダムは、まだ僕たちに何か隠している。……『完全な術士』って、何だろう?」
キングダムの出身ではないといいながら、いやに内情に詳しいジェラス。彼ならば、納得のいく答えを出してくれるのではないか。
「人命を冒してまで、そんなものを求める理由は、何ですか……?」
知らず知らずのうちに、ルージュは目の前の青年にずっと抱えつづけた疑問をぶつけてしまっていた。
しかし返ってきたのは、望んでいた答えではなかった。
「……キングダムに帰還して訊いてみたらどうだ」
「帰還のための扉は、使命を果たしたあとでなければ開かれません……」
リージョンシップを用いて正規に入国しようとすれば、まず審査にかかって阻まれる。
魔術を用いて移動しようにも、扉は強固に封印されている。強引にこじ開けようにも、ルージュひとりの魔力では不足していた。
時空を移動する特殊な技術であるため、魔術の資質を持たない者の力を加えることは暴走の危険があり望ましくない。
(『完全な術士』ひとりの魔力なら……いや、ブルーの魔力と二人分なら、もしかしたら)
扉を強引にこじ開けるという方法に、ブルーが素直に協力してくれるなどとは到底思えないが、彼に会ってみないことには先へ進むことは出来ない。
「君がどう考えていようが、ブルーが時空の資質を手にすれば対決を避けることは出来ないだろう」
運命からは逃れられないと指摘されて、はっとルージュが顔をあげた。
そこに、唐突に割って入る声があった。
「ブルーと申したか。その者ならば、先程ムスペルニブルへ行くと申したが」
声のした方を二人が振り返ると、巫女風の衣装を着た少女が立っていた。
幼い容貌に、古風な口調は不釣合いな印象を与える。
「指輪の君か……彼は時術の継承を望むか。ならばルージュが得ることになるのは空術の資質だな」
「それではそなたは……っ!」
「ルージュ、すまないが先に戻っていてくれないか。彼女と少し話がある」
少女は何か言いかけたが、ジェラスが半ば強引に遮った。
口調は穏やかだったものの、反対できない雰囲気があった。どうやら、ルージュには聞かせたくない類の話らしい。
(気にならないといったら、嘘になるけど)
何か不自然な感じはしたが、邪魔するわけにもいかないと思い、ルージュは神社を後にした。
ルージュが去った階段の方を見遣りながら、ジェラスが口を開いた。
「ブルーは」
ルージュがいずれ対峙する宿命の相手の名を口にして、いったん言葉を切った彼は、晴れ渡った空を見上げる。しかし、空を見上げるというよりはもっと遠くの……どこか遠い日の思い出を振り返っているかのように、ぽつぽつと言葉をつむぐ。
「時空の資質を得るために犠牲は避けられないとしても。それを知っていても、おそらくためらいはしないのだろうな……」
「そなた……それで良いのか? ……もしやあの者、何も知らぬまま、空術の資質に挑むことになるのかや?」
「あの子が……ルージュが空術の資質を得たいと訪れたのなら、案内を」
ジェラスは自分を見上げる少女に微笑を返す。背を向けると、石段の方へと歩き出した。
「わらわが『嫌だ』と申しても、聞き入れる気なぞないくせに!」
先程までと違い、幼さを感じさせる少女の叫びが聞こえて、ジェラスはびくりと肩を震わせた。
「……すまない……」
背中を向けたまま、穏やかな声でジェラスは謝罪の言葉を口にする。
「わらわはそなたに、謝罪の言葉を求めているのではない……!」
少女が求めているのは、魔道王国の術士を時空の試練に導くことを拒むことだ。
ジェラスが謝ったのは、彼女の気持ちを傷つけたことに対してだった。少女の怒りと悲しみの理由がわかっていても、彼は行動を改めるつもりはまったくなかった。
それがわかっているから、少女もまた遠ざかる背を追いかけようとはしなかった。
石段を降りきったジェラスは、赤い鳥居越しにはるかな高さにある神社を見上げた。
「私は、退くわけにはいかないのですよ……零」
闇の迷宮から抜け出し、仲間と再会した後。
宿での夕食を終え、部屋で休息をとっていたアセルスは、ふと身に着けていた装飾品――ユニコーンの涙に目をとめる。
(あれ……? 何だか、前より色が薄くなった?)
壊れるような乱暴な扱いはしていないつもりだったが、元の持ち主にきけば何かわかるかもしれない。
宵っ張りな印象はないが、あまり眠っている姿を見た覚えのない彼のことだ。少し遅いが、多分起きているだろう。
宿の個室をノックすると、やはりジェラスは起きていた。
「若い娘が、こんな時間に男の部屋を訪ねるのはあまり褒められた行動ではないが……どうした?」
「ごめん。ちょっと、気になって」
ヨークランドを訪れた際に譲り受けた、ユニコーンの涙を見せる。
「――ああ、これは。大丈夫、心配はいらない。濃くなっているなら問題だが、淡くなるのはそれほど珍しいことではないよ。おそらく、前の持ち主だった私の影響が抜けて、君に馴染んできたということだろう」
「そうなの?」
ユニコーンの涙は持ち主の気性の影響を受けて色合いが変わる――むしろ良い変化だと教えてもらって、アセルスは「それなら最初に教えてくれればいいのに」と小声で呟く。
少し、むくれた顔をしていたのだろうか。小さい子にするように、頭をなでられて、アセルスは驚いてジェラスを見上げた。
「本当は、君の旅に最後まで同行したかったんだが――すまない、アセルス。私には私の、なすべきことがある。試練の場には、私は行けない。だから――」
もしかしたら、彼はあの神社で、そっと別れるつもりだったのかもしれない。けれど、一度こうして戻ってきてくれたのは、さよならを言うためだったのだろうか。
穏やかな中に、何か強い意志の感じられる瞳。
引き止められるはずが無い。
「さよならは、言わないよ」
自分宛で無い別れの伝言だけ受け取って、アセルスは自室へ戻る。