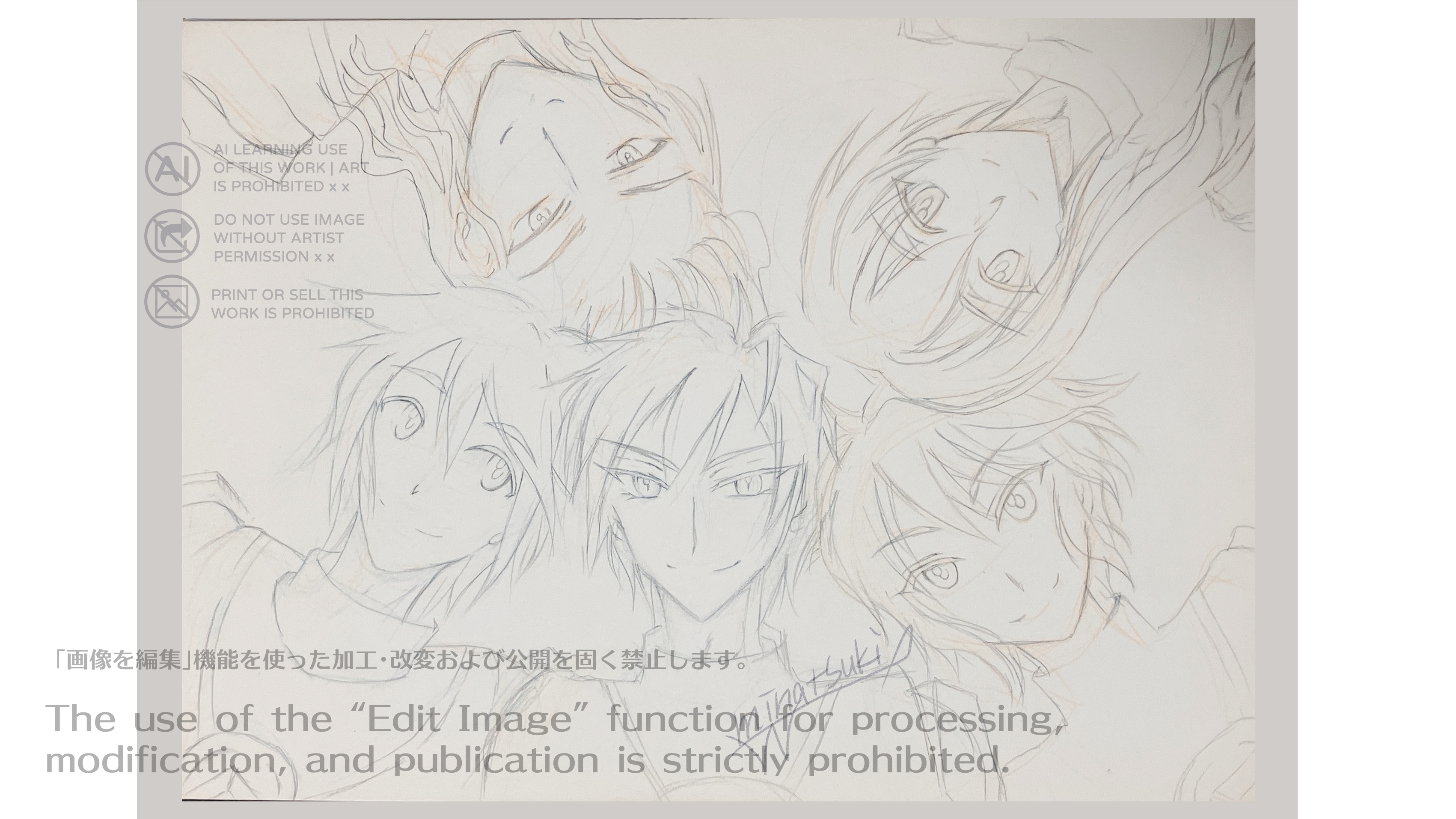呪歌
ジェラスはルージュに手をかざし、癒しの魔力を注ぎ込んでいた。
「疲労に回復魔法は効かないが、気休め程度にはなるだろう」
「……何かさぁ、ジェラスって、色々言ってる割にはルージュに甘いよね」
「否定は出来ないな」
アセルスの指摘に、『甘いのはわかっているが、そうしたいのだから仕方がない』とジェラスは肩をすくめた。
苦笑して答えた青年は、ルージュの顔色にかすかに血の気が戻ったのを確認するとふと真顔に戻った。
「無茶はルージュに限った事ではないよ。……正直、そんな、君自身が傷つくような戦い方は感心しないな。お嬢さん」
動かないで。すぐに終わるから――と断って、ジェラスはアセルスの傷口に手をのばした。
(あ、……なんだか、あったかい。ルージュの『スターライトヒール』とはちがうけど)
言われてみれば、こうして傷を癒してくれる仲間がいるから死なずにすんでいるのかもしれない――とアセルスは少し反省した。
「はい、終わり」
はじめたときと同様、ジェラスは唐突に手を離した。
ふわりと微笑む青年を見て、ああ、やっぱり――とアセルスは思った。
しかし、ぼんやりとおぼろげながら形になりかけていた考えは、割って入った声によって霧散してしまう。
「こりゃ、これ以上進むのは無理かぁ? 盾のカードはまた今度ってコトで今日はいったん戻った方が良いんじゃねェか」
(いま……なにか、わかりかけてたんだけど)
ヒューズの言葉は、考えている余裕はないと告げていた。外は荒れ狂うブリザードに加えてモンスターの群れ。
現在のパーティーで強引に進んだところで遭難するのがオチだろうとの、ヒューズのもっともな指摘に対して、アセルスは申し訳なさそうな表情でまだ顔色の冴えないルージュにちらりと視線を送った。
「できれば、これだけはやりたくは無かったが――」
そう呟くと、ジェラスは洞窟の出口へと歩き出した。外へ踏み出す手前で立ち止まって、いったい何をするつもりかと訝る一同に呼びかける。
「悪いが、皆少し下がっていてくれないか。……それから、お嬢さん方。目を閉じていた方が良い」
これからジェラスが何をするつもりなのか気にはなったが、一同は素直に指示に従った。
ひとり吹雪の中に立ったジェラスは――すぅ、と一呼吸つき背筋を伸ばした。
突如、涼やかなバリトンが雪山に響きわたる。
彼の口がつむぐのは、呪文の詠唱とは異なる美しい旋律。
風の音にかき消されることなく続けられるその詩は、アセルスやヒューズだけでなく、白薔薇姫ですら知らない言語のようだった。
「何――これって、歌……?」
「――何だろう、この歌……懐かしい――?」
「ルージュ、知ってるの?」
ジェラスの歌に、何故か強く惹きつけられるようなものを感じたルージュは、歌声に宿る強い魔力を感じてはっとする。
程なくして戻ってきたジェラスは、もう外に出ても大丈夫だとアセルスに告げた。
「……!!」
外に出た四人は、言葉を失った。
雪の上、いたるところに先程までモンスターの群れだったものの残骸があった。
気付けばいつのまにか吹雪も止んでいる。
いったい、何をしたのかと疑問のまなざしで見つめる一同に対し、ジェラスはちょっと困ったような複雑な微笑を浮かべる。
「――古い詩だよ。ある女性を讃えた、遠い祖国を想う歌だ。女神だという説もあるが」
そういうことを聞いてるんじゃなくて、と、さらに詰め寄るアセルスに答えたのは、当の本人ではなくルージュだった。
「『呪歌』、でしょう? さっきの、あれは。『激しい歌声は嵐をも鎮め、穏やかな歌声は安息をもたらす』――古の技。キングダムの書庫で、記録を目にしたことがあります」
魔導王国の資料にも数名の使い手の存在が残るのみで、具体的な個人名に至っては一切不明のため、実在するのかどうかも疑問視されていた幻の技術。
まさか、その使い手に会えるなんて――とルージュは感嘆の呟きをもらした。
「でも、こんなすごいのが使えるんなら、どうして今まで使わなかったの?」
アセルスのもっともな指摘に、ジェラスはちょっと渋い顔をした。
「……ここがどこだか解っているな?」
「どこって、ムスペルニブルの――あ、そっか」
「あのさぁ、俺にもわかるように説明してほしいんだけど?」
何やら小難しいルージュの講釈で頭痛を起こしかけていたヒューズが割って入ると、ため息をひとつついたジェラスは答えた。
「私としては要らぬ危険は避けたい。やむを得ずさっきの技を使ったが――『呪歌』というだけあって『歌わなければならない』という制約がある。当然、音波耐性のある敵には効かない。残りは雪崩でまとめて片付いた」
合図をするまで外に出るな――といったのはそういうことか、とヒューズが納得するとジェラスは無言でうなずいた。
できればこれっきりにしたい、あてにするなという態度に、アセルスが他意はなく素直に感想を述べる。
「ふぅん? もったいないね? ……綺麗な声なのに」
「誉め言葉だと受け取って礼は言うが、嬉しくはないな。――いやなものはいやだ。雪山を出ても、2度と使わない」
渋面を隠せない青年と、何かまずいことでも言ったのかと焦る少女の傍らで、仲間たちが思わず吹きだした。